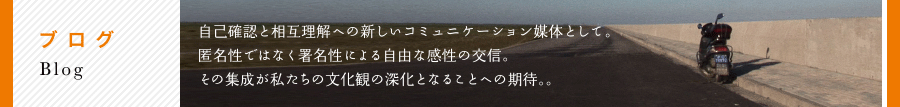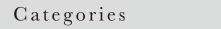2022年1月17日

『老子』を読む(二)
井嶋 悠
今回は『老子』の第2章から第5章までです。
第2章
美の美たるを知るも、これ悪(醜)のみ、善の善たるを知るも、これ不善のみ。
有無。難易。長短。高下(高低)。音(楽器の音色)声(肉声)。前後。
聖人は無為(無為を為す)のことに拠り、不言の教えを行う。
辞(ことば)せず。有せず。恃まず。居らず。(栄光・誉)去らず。
◇絶対評価と相対評価。凡々たる人間教師が絶対評価することの難しさ。「秀」としたいが、何をもってそうできるか。平生評価と試験(レポート等提出を含め)評価、例え25人学級でも可能か。それが1学年3クラスとして75人。絶対評価に挑むことで高まる教師力?
偏差値評価の再学習の必要?或いは「ヒトがヒトを評価する」ことの必然性と成績評価について。
教師と生徒、その一期一会は可能か。平凡な教師と非凡な教師、と考えた時、私が出会った非凡な教師は唯一人?
第3章
賢を尚(たっと)ばざれば、民をして争そわざらしむ。
無為を為せば、即ち治まざるなし。←民をして無知無欲ならしめ、その知者をして敢えて為さざらしむ。
◇教育における欲望とは何か。上になること。競争という欲望。そこで問われる学力観。塾・予備校の学力観は、社会の、学校社会の学力観があって成り立つはずであるが、今逆転しているのではないか。
敢えて塾・予備校を廃し(禁止)すれば、そこに何が起きるだろうか。教師一人一人の、学力観、競争観が問われることになるのではないか。その時こそ、客観的且つ総合的入学試験改革が視えて来る。
第4章
道は虚しきも、これを用うればまた満たず。淵(えん)として万物の宗たるに似たりその光を和らげて、その塵に同す。⇔「和光同塵」
◇真に優れた者は、際立ったことを為さない。50年ほど前、数学の研究者を目指す、長崎県の離島出身の人物と出会い、懇意になった。温厚篤実、実に穏やかな人物であった。親しく話さない限り、彼が途方もない優秀な道程を歩み、だからこそ苦悶することもあった人物であることを誰も気づかなかっただろう。彼は10年後任地で没した。
第5章
天地は仁ならず、万物を以って芻狗(すうく)と為す。聖人は仁ならず、百姓を以って芻狗と為す。多言はしばしば窮す。⇒「学を絶てば憂いなし」、中を守るに如かず。
◇「あの学年は、クラスは云々だった」と学年やクラス概評を教師はよくするが、これほど“個”を切り捨てた表現はないとも言える。
多言(おしゃべり)は醜い。生徒は黙って瑞々しい感性で見抜いている。生徒たちの馬耳東風。先の話題も多言の一変形。
| 新しい投稿 | ブログトップ | 前の投稿 |