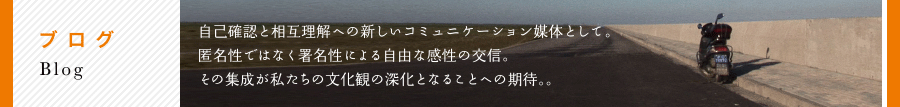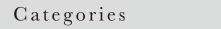2022年3月20日
井上 邦久
最高気温が連日新記録を更新して、一気に草木の芽が張る季節が来ました。艸という形に由来する草の字には春が内在しています。そして志貴皇子の歌、
「岩走る垂水の上のさわらびの萌え出ずる春になりにけるかも」
を思います。
万葉集には「石激 垂見之上乃 左和良妣乃 毛要出春尓 成来鴨」とあり、ここの佐和良妣は「蕨」か「薇」か?と酒友中国文学者桑山竜平に訊かれた万葉学者の大浜厳比古は『万葉幻視考』(集英社)に啓発に満ちた酒席噺を綴っています。
味わいのある酒の上での話を、早くみなさんと楽しみたいです
福沢諭吉も酒豪であったと聴いています。
門閥にこだわる中津藩の狭量さに嫌気がさして、蘭学修業先の長崎から故郷中津に戻らず、大坂の緒方洪庵の適塾に直行して頭角をあらわしています。
灘や伏見の酒にも馴染んだ諭吉をはじめ、貧しい書生たちの面倒をみたのが緒方八重さんその人です(億川百記の娘、摂津国西宮名塩に生まれ。洪庵が適塾を開いた頃に十七歳で結婚)。
福沢諭吉の同郷の後輩、田代基徳(陸軍軍医校長などを歴任)は特に貧乏で、按摩で糊口を凌ぎながら猛勉強したとか。常に空腹で、深夜に樽の餅を盗もうとして、八重さんに出くわし夜具を被って隠れていたら、八重さんから掌に沢山の餅を載せて貰ったという逸話を、「中津藩出身の蘭学者」(川嶌眞人『大阪春秋』「緒方洪庵生誕200年特集」号)でとても味わい深く読みました。
緒方洪庵の偉業を要約すると、以下の三点になるのではないかと思います。
先ず、適塾を開き福沢や田代のような多くの俊才を育成したことがあります。姓名録の記録だけで637名とのこと。
次に、町医師や町人と除痘館を開設して、牛痘種痘の施療とワクチン分苗ネットワーク(池田・伊丹・灘・西宮など)を民間主導で築いたことです。
三点目として、1858年のコレラ大流行に際し、長崎の蘭館医ポンペの口授治療法(松本良順訳)に並行して、医訳書『虎狼痢(コロリ)治準』を緊急出版したことが挙げられます。ポンペは阿片やキニーネを大いに推奨しているのに対し、洪庵は使用を否定しているわけではないものの多量な使用には異論を唱えていたようです。
以上の事柄は、古西儀麿『緒方洪庵と大阪の除痘館』(東方書店)などの医学史書に詳しく、また『ぼくらの感染症サバイバル 病に立ち向かった日本人の奮闘記』マンガ:加奈、監修:香西豊子(いろは出版・2021年12月出版)で楽しく読めます。
小学高学年以上からを対象に監修したとお聴きしましたが、緒方洪庵からジョン・スノウ(1854年、ロンドンでのコレラ流行を終熄させた「疫学」生みの親)まで幅広く書かれています。
未来からタイムスリップしてきた緒方洪庵の子孫が、中学生と古代から現代までの疫禍の現場に飛んで人々の奮闘を知る筋立てです。
2021年10月『牛の話』で触れた仏教大学香西春子教授の講座は、対面教室で、色々な貴重な医学史料を手にさせてもらい、質疑応答も無制限でした。随分お得な疫学史と公共衛生の入門コースでした。
スペイン風邪の終熄後100年の間、天然痘撲滅を初めとする感染症との奮闘を「征圧」と過信して、感染症用病床を減らし続けた経緯を教わりました。現在も適塾のお膝元で感染症病床の不足が何度も伝えられる背景を考えるヒントになりました。
また、西洋医学の日本導入期に貢献したポンペ医師の写真を指し「偉丈夫で胸を張っていますが、意外と若くて30歳前後だったのです」というコメントは新たな発見でした、軍医出身だったポンペが、明治政府の医学・衛生行政にどのように影響したかも考えさせられました。
緒方洪庵は幕府の奥医師(将軍の侍医)に招かれ、渋々大坂から江戸に移り、その翌年(1863)に八重と九人の家族を残して没しています。文久三年、京の壬生寺に新撰組が屯所を置いた年です。八重さんは遺児や親族の子を幕府及び新政府の欧州派遣留学生として送り続ける一方、戊辰の戦の時には横浜に避難し、その後帰阪して適塾に住んでいます。
1873年には除痘館がその役目を終えて閉鎖され、1875年からは八重さんの隠居部屋となりました。
適塾は保存対象の建築物となり、その脇の路地を南へ抜けた除痘館跡、大阪市中央区今橋三丁目のその土地には緒方病院ビルが建ち、その4階に除痘館記念資料室があります。
「適塾の偉大さは、緒方洪庵の偉大さによるものであるが、病弱の洪庵と多くの門人たちの世話を一手にひきうけて、門人から慈母のように慕われた八重夫人の内助の功をわすれてはならない。」、これは伴忠康の『適塾をめぐる人々―蘭学の流れ』(創元社)の巻頭に記された言葉です。
明治十九年二月七日、八重さんは62歳で逝去。孫の緒方銈次郎氏の文章によると、「葬儀の式は空前の盛儀を極め、親戚知己を始め適塾門下多数の参列を受けて阿倍野に送られた。葬列の最前列が日本橋付近に差しかかった時、棺は未だ北浜の拙齋宅を出て無かった程に長かったといふことである。」とあります。
もともと近場の長柄村で葬儀を行い、北区寺町の龍海寺の洪庵の墓に納骨をする予定が、参会者が予想以上に多く(二千余人とも三千人とも)直前に阿倍野(天王寺村)斎場に変更されています。
翌月、福沢諭吉は東京から龍海寺に参り、お供の慶應義塾員の酒井良明を止め、「これは私のすることだ」と自ら墓石を洗いあげた、と伝えられています。
これより先、明治十八年十月二日、五代友厚の葬儀は中之島の邸(現日本銀行)から淀屋橋南詰を東に・・堺筋南へ、住吉街道鳶田より東へ、天王寺村埋葬地へ着す。・・大阪府に於ける紳士縉商と称せられる者は悉く皆会葬し、その数実に四千三百余人の多きに達し、大阪府空前の盛儀を呈したり、と伝記にあります。
2022年3月19日
井嶋 悠
途方もない迫力で心に迫って来ます。人生に一冊で老子を挙げる人が少ないことが得心できます。私もそうなりたいです。
今回は11章から15章です。
第11章
有の以って利を為すは、無の以って用を為せばなり。
←埴(つち)をうちて以って器を為る。その無に当たって、器の用なり。
「無用の用」(『荘子』)
◇学校は、他の組織社会同様、その学校創設目的に合った教職員が構成し、そこに共振する生徒・保護者が集まる。そこに有用無用はない。しかし、現実はそれぞれの有用な人のみに視線が向く。これは「個を活かす」との教育の根本から乖離している。しかし、私たちにそれほどの余裕(ゆとり)があるだろうか。もし、この余裕が学校に満ちれば、教職員を含めた不登校(登校拒否)は確実に減るのではないか。
第12章
五色(青・黄・赤・黒・白)は、人の目をして盲ならしむ。五音は人の耳をして聾ならしむ。
聖人は、腹を為して目(感覚)を為さず。故に彼れを去(す)てて此れを取る。
◇学校にはそれぞれの創設理念がある。公立校も然りである。しかし、少子化、学校間競争の過剰や公益性を無視し、なりふりかまわぬほどの生き残りを、或いは統合と称する一方の消滅を図る。私学で、一時期?生き残りのため、何が何でも進学実績を、男女共学化を目指すことが露わになった。その内、何校が現在正常な学校の態を為しているだろうか。
人間の平等、個の尊厳を言うならば、学校格差を無くす根源的解決をなぜ考えないのか不思議でならないのか、かねて来思っていたが、現実のヒト社会に、いかにそれが夢物語であるかを思い知らされて来た。今も、である。
第13章
寵辱(ちょうじょく)(寵愛と屈辱)には驚くが若し。大患(たいかん)を貴ぶこと身の若くなればなり。が身我が命あっての世事と治世。
吾に大患有る所以の者は、吾に身有るが為なり。吾に身無きに及びては、吾に何の患い有らん。
◇当然のことながら教師も多種多様である。“デモ・シカ”教師もあれば、“サラリーマン”教師もいる。後者の表現があること自体、教師は聖職者との意識の表われかもしれない。
「子ども(生徒)のためには死んでも構わない」旨言った、校長がいた。言われた私は「どうぞ、頑張ってください」と応じ、ますます嫌われた。
私は、その校長の言葉に酔う性と権威性を苦手としていたので、皮肉でそう応えたのであって、校長がいかに生真面目であるかの証しにもなったのかもしれない。
その校長、その後、いろいろな学校を渡り歩く人生を送るのだが、その根幹は常に同じだった。その根幹、私など辛くて到底耐えられない。そのような類のヒトは他にもいたが、決して多くはなかった。
と言いながら、あの「サッカー部」顧問時代は、一体何だったんだろうと回顧することがある。
第14章
「夷(視れども見えず」「希(聴けども聞こえず)」「微(とらうるも得ず)」。この三つのものは詰を致すべからず。故(もと)より混じて一と為る。その上は明らかならず、その下は昧(くら)からず。⇔『無状の状・無物の象・惚恍。』
これを迎うるともその首(こうべ)を見ず、これに随うともその後(しりえ)を見ず。
古えの道を執りて、以って今の有を御すれば、能く古始(始源)を知る。
◇他人に個人的なことを質問されるのは、非常な緊張を強いられる。自身の中に明快な答えが即座に出せるほどに持っていればいいのだが、
私の場合、なかなかそうも行かない。その一つが「先生は、どうして国語の先生になったのですか。」ここには二つの苦難があって、一つはなぜ先生に?であり、もう一つはなぜ国語なのか、である。要は非常に不謹慎な教師なのだ。
それがあってか、大人同士の会話で「先生」と呼ばれることが、今もって円滑に私の中に入って来ない。
国語は曖昧な教科と言えばそうである。あの文法でさえ、また漢字でさえそうで、正解が幾つかある。いわんや、読解問題でも微妙なことは常である。作文となれば尚更である。それが明解な正解を求める生徒にはイラつかせる。評価の客観性と主観性に関して、国語科評価は微にして妙で、だから甚だ後付ながら私は国語を選んだとも言える。
その面白さを生徒が味わうことで、国語はすべての教科の基層的滋養になれるのでは、と我田引水している。それは、現代(表現・作品)を現代人としてだけで視るのではなく、古代人の眼を意識する広さを以って。
ところで、入学試験での、考える力を測る論述形式問題導入。今更何を、の主題ながら、各教育現場の評価する側の教師は、この一連の動き、報道をどうとらえているのだろうか。
第15章
古えの善く道を為す者は、微妙玄通、深くして識るべからず。
此の道を保つ者は、盈(み)つるを欲せず。⇔「持してこれを盈たすは、その已むるに如かず」
微妙玄通。予として、猶として「猶予」(ためらう)。柔弱不争。
◇微妙玄通の哲人には、温厚篤実なイメージが色濃くある。教師も然りである。私自身、それぞれの職場でそのような人物と何人か出会った。私自身、気が短く、深謀遠慮に乏しいことを、その時々に自覚するだけであった人間だったので、なおさらそのような人物を尊崇した。そして、その人物たちは等しく己が宗教を持っていた。それは、仏教であり、キリスト教であった。宗教の巨(おお)きさを身をもって実感しつつも、私はその宗教の門の前でうろうろするだけであった。今、無宗教徒であり、であった自身を顧み、宗教にどこか惹かれつつも、このまま生涯を終える私なのだろう、とそこはかとなく思っている。
その中の何人かは既に天上に昇られているが、何人かの方とは今も交流が続いている。
2022年3月4日
井上 邦久
2020年末から2021年初頭以来、集英社新書『人新世の「資本論」』は読者を増やしているようだ。1987年生まれの著者、斎藤幸平氏を画像で見る機会も増えてきた。
冒頭から、SDGsは「大衆のアヘン」である!と書き始める。そして・・・かつて、マルクスは、資本主義の辛い現実が引き起こす苦悩を和らげる「宗教」を「大衆のアヘン」だと批判した。
SDGsはまさに現代版「大衆のアヘン」である、と続く。SDGsについての議論は別にして、何故SDGsに「アヘン」が比喩的に用いられるのか愚考してみた。そして、その流れでアヘンの深みにはまりそうで、始末に負えない予感がしている。
アヘン(阿片・鴉片)はケシから採取した汁を乾燥させ製造する。モルヒネ、コデイン、テバインなどのアルカロイドを含む。医学用途として鎮痛効果や一時的な昂揚感・多幸感を感じられるとされるが、習慣性・中毒性に陥ると心身の滅亡に到る。
『アヘンからよむアジア史』内田知行・権寧俊〈編〉(勉誠出版・2021)に「乱用薬物」を取り締まるための法律として以下の整理がなされている(一部省略)。
・アヘン関係:生阿片取締規則(1870)⇒旧阿片法(1897)⇒あへん法(1954)⇒現在・モルヒネ・コカイン・向精神薬関係:モルヒネ・コカインおよび其の塩類の取締に関する件(1920)⇒麻薬取締規則(1946)⇒麻薬および向精神薬取締法(1990)⇒現在
・大麻関係:大麻取締規則(1947)⇒大麻取締法(1948)⇒同法改正(1953)⇒現在
・覚せい剤取締法(1951)⇒現在
室町時代に南蛮貿易によって渡来したケシ・罌粟(アヘン・阿片)が何故か津軽にもたらされ(宣教師が治療用などで帯同したか?)、津軽はケシ栽培・アヘン精製・販売の拠点となった。津軽藩の奨励策により特産「一粒金丹」としてブランド化された。
ここからは陸羯南研究会で知り合った松田修一氏(東奥日報前特別論説委員・津軽在住)から頂戴した参考URLとご教示を抜粋する。
https://tsugaru-fudoki.jp/digtalfudoki/ichiryukin/
(森鴎外の)『渋江抽斎』は冒頭に「津軽地方の秘方一粒金丹というものを製造して売ることを許されていたので、若干の利益はあった」と書いていますが、月に百両の収入は若干ではありませんね。
一粒金丹は藩統制品でしたが、藩士は入手可能であり、他藩への土産品として持っていくことも許されたため、瞬く間に全国ブランドになりました。江戸市中にも(たしか)2軒の専売所開設が許されました。うち1軒が渋江家だと思います。
抽斎が医師として名をなしたのも、一粒金丹が万能の妙薬として人気がすこぶる高かったからでしょう。【中略】それで、ちょっとだけ調べてみたところ、名古屋大学の紀要『ことばの科学』(11号:1998年)に、次の論文が掲載されていることが分かりました。
「成田真紀 津軽医事文化資料と池田家文庫の撞着 ―渋江道直の一粒丹方并能書をめぐって―」。青森県内の図書館は所蔵していないようなので、国会図書館からの入手が可能か否か、聞いてみようと思います。まずは、同書を引用しているネット情報を見つけたので関係部分を要約します。
1837年(天保8年)ころ、大坂道修町の薬屋の奉公人が、取引先回りの際、津軽でケシ栽培やアヘン製造法を伝習し、種子を持ち帰り、摂津の国三島郡でけし栽培を始めた。・・・
だそうです。茨木ですね!!
松田さんのお蔭で、津軽⇒大坂道修町⇔摂津国三島郡=茨木がつながった。
『新修 茨木市史 資料集7 新聞にみる茨木の近代 三島地域朝日新聞記事集成』には以下のように纏められている。(1887.9.8)
・阿片製造の濫觴:天保八年島上郡西面村の植田五十八が同村玉川近傍字北の小路にて白色単弁の罌粟を栽培、之を以て阿片を製錬したるを創始とす。五十八の弟四郎兵衛は道修町の薬舗近江屋安五郎方に雇われ,商用ありて北陸奥羽の地方に到りしが津軽に於て阿片を製造するを一見し罌粟の栽培及び阿片に製錬する方法を習い、兄五十八に伝ふ・・・
・島下郡福井村の彦坂利平の弟治平が道修町の薬舗榎並屋三郎兵衛の養子となり阿片の買い入れの為、年々陸奥の津軽地方に赴しが、製造法の伝習を受け、種を兄の利平に授けて阿片製造の業を慫慂せり、天保十二年同村字秋浦にて罌粟栽培、同村田中庄三郎・南浦孫七等に伝えついで中河原・安威その外の諸村に伝わり遂に今日の如く西面村(高槻藩領:現高槻市)、福井村(一橋家領:現茨木市)ともによく似た経路で、津軽から大坂道修町(現大阪市中央区)の薬種商が種子・技術を移入し、摂津で下請け栽培をさせ、「一粒金丹」の津軽藩独占を崩そうと試みた構図が見えてくる。
若干後発であった福井村は「最良の阿片を製出するは島下の福井村にて同村の品は尤も多量のモルヒネを含めりとのことなり(同1884.11.21)」とある通り、明治時代の半ばには評価を上げている
『日本の阿片王 二反長音蔵とその時代』 倉橋正直(共栄書房 2002)には府県別生産1921年度(大正十年度阿片成績『艸楽新聞』1922年7月1日から転記)として下表があり
ケシ栽培人員 阿片納付人員
大阪 3,492(人) 5,146(反) 大阪市 1(人)岡山 899 540 三島郡 4,013
和歌山 748 714 豊能郡 202
京都 285 224 北河内郡 21
兵庫 190 186 中河内郡 4
奈良 29 17 南河内郡 4
この統計によれば大阪のシェアが圧倒的であり、その中で三島郡(福井村・安威村)が群を抜いている。
また、第一回大阪府実業功労者として個人表彰の新聞記事がある。
(1922年2月11日)
中山太一 (中山太陽堂=クラブ化粧品) 化学品製造輸出伸張
木谷伊助 朝鮮貿易伸張
芦森武兵衛 (精工舎) 綿編及び紡絃の創
辻本豊三郎 (福助足袋) 足袋の改良と公益助
二反長音蔵 罌粟栽培普及(年産額
千五百貫
賠償金額参拾万円)
この二反長音蔵(にたんちょう おとぞう。旧姓川端音二郎が二反長家のレンと結婚)が大阪府三島郡福井村を拠点に、ケシの栽培・採取方法・モルヒネ含量向上の技術改良に努力し、栽培面積の拡大に尽力した成果が上記の地域別シェア記録や公的な顕彰に繋がっている。一方で、アヘン生産と戦争とは密接な関係がある。軍縮平和の時代は需要が低調になるが、軍拡戦争の時代はアヘン生産が連動して増加している。
1914 第一次世界大戦 軍需用モルヒネの需要増⇒原料アヘンの払底1915~1919 内地・朝鮮でケシ栽培の拡大 (二反長音蔵の出張指導 計5回)
1918 第一次世界大戦終結 軍需用モルヒネの需要減⇒原料アヘンの滞貨⇒ケシ減産
1931 満洲事変 増産体制へ転換。日中戦争/1937、第二次世界大戦/1941 増産強化1945 GHQより禁止令
1954 ケシ栽培の復活(戦前の10%の戸数。1960)⇒厚生省政策変更。限定栽培
ケシ栽培に連動するアヘンからモルヒネ精製の変遷を簡単にメモすると、
1915 星 一創業の星製薬が国産化成功(台湾アヘンの精製・台湾総督府との提携)
1917 内務省の指示で、大日本製薬、三共、ラヂウム商会に技術の公開認可
朝鮮で半官半民の大正製薬(国策会社であり、現大正製薬とは別)を設立
大正製薬の招請で、二反長音蔵が開城京畿道方面で指導調査。
1918 第一次大戦終結⇒モルヒネ輸入再開・相場下落⇒朝鮮でモルヒネを一般販売
1928 増産体制
1933 大増産体制
『新修茨木市史 資料集7 新聞にみる茨木の近代 三島地域朝日新聞記事集成』からの関係記事を取り上げると、安東(現遼寧省丹東市)、長白地区、張家口、旧熱河省などへの二反長音蔵の足跡を戦争末期まで追うことができる。
・阿片王国といはれる大阪府三島郡の阿片栽培者ハ毎年増加するばかりで、近来裏作といへば昔なじみの麦、菜種をすてて阿片を作るようになった。・・・裏作は全部阿片に・・・
茨木署部内調査(17町村):1,456名、226.4町歩、631貫、
137,529円
豊川、三島村、福井村、春日が多いが、福井村の生産性が突出 (1928.4.20)
・内務省「阿片栽培制限令」撤廃決定。栽培免許相続人の栽培も従前通り(1929.8。8)
・二反長音蔵、安東区阿片綜批發処の招請、東辺道長白府方面で指導視察。(1934.8.23)
・福井村で数十年ぶりに阿片密売者根絶。神戸方面の不正ブローカーの潜入などで、純朴な農村から夥しい違反者が摘発され昨年の如きは88件検挙 (1936.10.1)
・「罌粟増産協議会」が9月5日茨木中学校で各町村長、農会長、厚生省、府農務課参集。
・二反長音蔵、蒙古政府の懇望で、罌粟栽培と阿片製造のため令息の半君と29日出発。
原始的な大陸の罌粟の画期的増収のため種子、採汁法の改良により戦時下重要な阿片増産にご奉仕する。(1943.6.27)
※茨木ゴルフ場(農地化)開墾着手(1943.8.14)
二反長音蔵の長男の二反長半(にたんおさ はん、と改名)の遺作となった、『戦争と日本阿片史 阿片王 二反長音蔵の生涯』(すばる書房)には、「1943年、二反長音蔵(当時70歳)に蒙古連合自治政府から主席徳王の名で招聘状が届いた」とあり、「これが最後の御奉公や。蒙古にうんと白い花を咲かせてやったるで」と書かれている。村の裏作収益を上げて、「一日一善運動」を行いながら、国内外で水はけの良い南向きの傾斜地を探し当てては熱心に栽培指導を行った二反長音蔵は「大陸で被害を受ける者」への影響をどこまで意識していたであろうか。
伝記の著者の二反長半は。旧制茨木中学の先輩である川端康成や大宅壮一に憧れ、戦前から児童文学の創作や伝記小説、歴史小説を執筆。最晩年に父親の伝記を脱稿した直後に倒れ、出版を見ずに急逝している。
ポプラ社や小学館の「こども伝記小説シリーズ」で、作者を意識せずに、二反長半の作品を読んでいる児童が多いかも知れない。
モルヒネなどアルカロイド系薬品の国産化開発に尽力して、星製薬をトップ企業にした星一社長の栄光と没落を、長男の星新一は、小説『人民は弱し 官吏は強し』にしている。
そのなかに「無理に考えたあげく、やっと被害を受ける者のあることに気がついた。阿片吸飲者たちだ。煙膏に含まれているモルヒネの量はかわらなくても、味がいくらか落ちることになるかもしれない。それと、インドの阿片業者だ。しかし、これくらいの犠牲は仕方のないことだろう。(新潮文庫版)」という一節を忍ばせている。
星一は後藤新平の台湾阿片漸減政策と表裏一体となって事業を伸ばしたが、後藤新平の後を襲って政界や官界の主導権を握った加藤高明以下の官吏・政治家に追い落とされた。
星一には商品開発、利益追求そして自社存続をかけた裁判には注力しても、阿片吸飲者への影響は意識のなかになかっただろうか。
ケシ・アヘンの世界に生きた二人の父と、多くの屈折を体験して文学に活路を見いだした二人の息子の自らの父親についての文章は重い。
歴史・社会研究分野からは、『日中アヘン戦争』(江口圭一・岩波新書)が初学の出発点となり、上記に引用した倉橋正直氏の福井村のフィールドワークや『アヘンからよむアジア史』内田知行・権寧俊〈編〉の視点の広さに多くを学んだことを附記し感謝したい。